菜の花はり灸院整骨院の青木です。
潰瘍性大腸炎は、2024年には患者数が27万人を超えるといわれており、厚生労働省からも難病指定されています。原因不明の腹痛や下痢で、日常生活に支障をきたしている方も多くいらっしゃいます。本日は、潰瘍性大腸炎の改善において「控えるべき食事」と「体質改善」がどれほど大切かについてお話しします。


控えるべき食事は三つあります。それは「砂糖」「小麦粉」「乳製品」です。
なぜこれらを控えるべきなのか、順に説明していきます。
■白砂糖を控えることの重要性


まず最初に控えていただきたいのが「白砂糖(精製された砂糖)」です。甘いものは腸に強い刺激を与え、腸内環境を乱すことで炎症を悪化させると考えられています。
白砂糖は清涼飲料水、アイスクリーム、お菓子など、多くの加工食品に含まれています。てんさい糖やきび砂糖のような自然由来の甘味料はまだ良いですが、精製された白砂糖は避けたほうが無難です。
実際、白砂糖をやめるだけでも腸の調子が良くなったという声は少なくありません。甘いものが好きな方にとってはつらいかもしれませんが、症状が落ち着くまでは徹底して控えることが大切です。
東洋医学では「潰瘍性大腸炎になりやすい体質の人が砂糖(甘いもの)をとることで発症する」と考えます。つまり、体質と食生活のかけ合わせによって病気が現れるということです。まずは「甘いものを食べない」と決めて体質を整えていくことで、潰瘍性大腸炎の改善は難しくありません。
■グルテン(小麦製品)にも注意を


次に避けたいのが、グルテン――小麦粉に含まれるタンパク質です。グルテンは小麦粉をこねた時に生まれます。パンのもちもち感やうどんのコシなどは、このグルテンによって生まれ、食べる時においしく感じられます。パンやパスタ、うどん、ケーキなど、グルテンはさまざまな食品に含まれており、現代の食生活に欠かせない存在となっています。
しかし、このグルテンの粘りは、消化の過程で腸の壁に粘着し、腸内環境を乱す原因となるのです。「リーキーガット症候群」と呼ばれる、腸の粘膜が損傷し小さな穴が開いてしまう症状を引き起こすこともあります。すると、未消化の食べ物や悪玉菌などの毒素が血液中に漏れ出し、全身に炎症を広げてしまいます。
このリーキーガット症候群は潰瘍性大腸炎やクローン病とも深く関係しており、大腸の悪化や慢性化の一因となることが分かってきました。
■乳製品(カゼイン)にも注意を
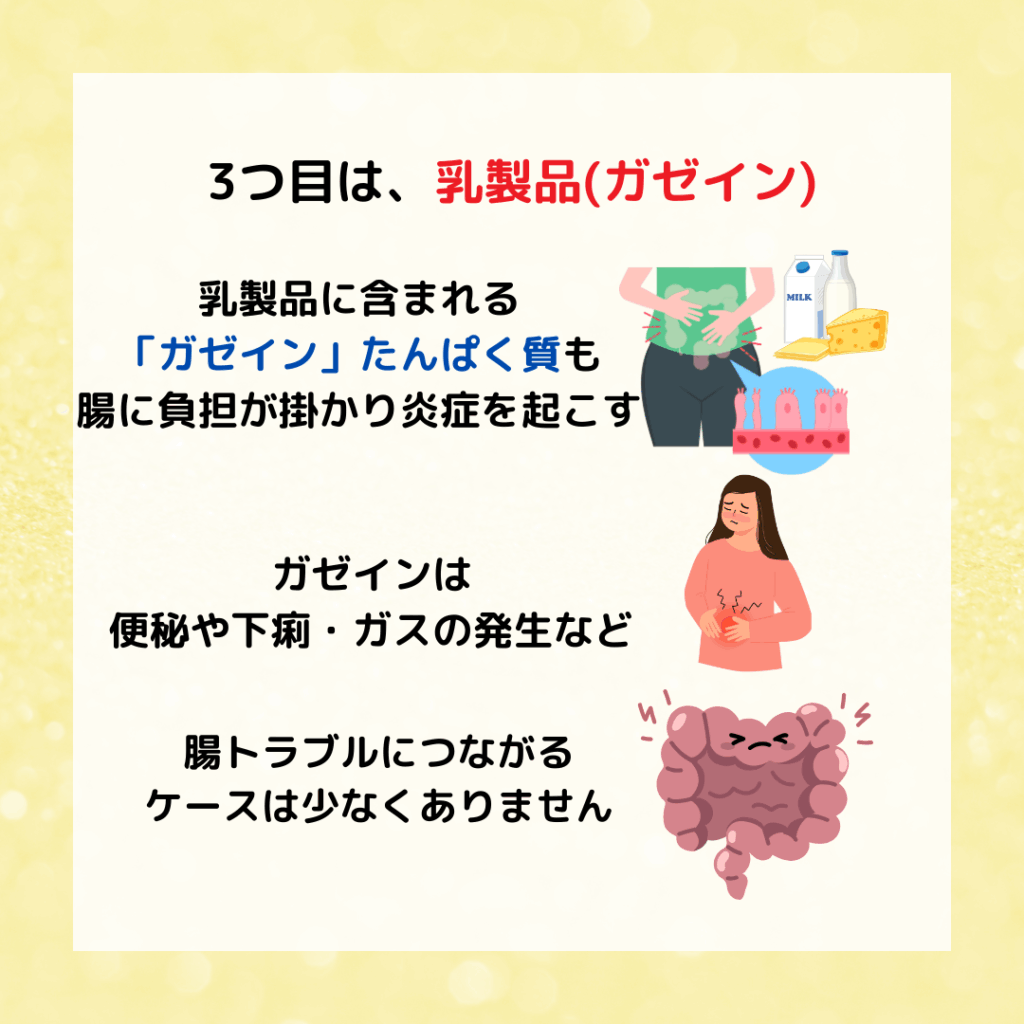
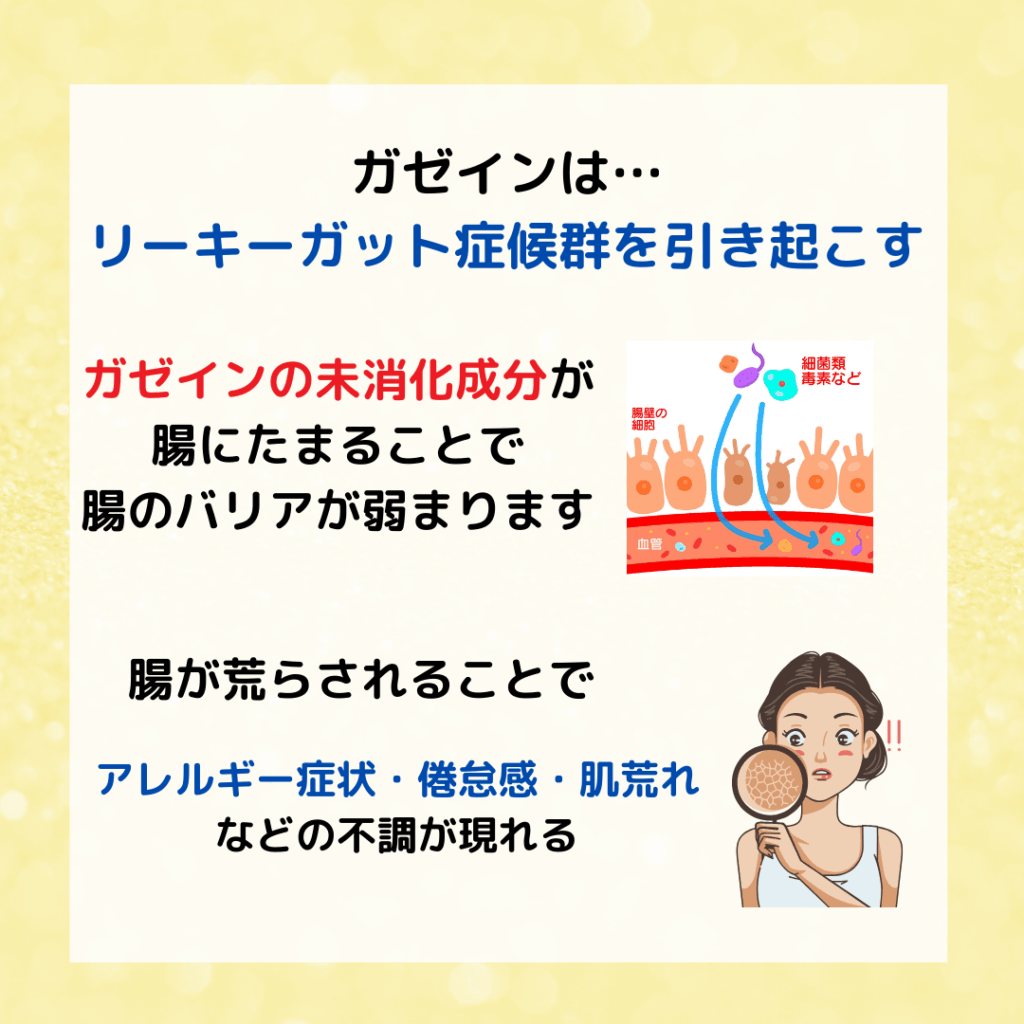
乳製品に含まれる「カゼイン」というタンパク質も、腸にとっては負担となることがあります。カゼインは腸内で炎症を引き起こす可能性があり、便秘や下痢、ガスの発生など、腸のトラブルにつながるケースも少なくありません。
また、カゼインの未消化成分が腸にたまることで腸のバリア機能が弱まり、リーキーガット症候群を引き起こすリスクも高まります。これにより、アレルギー症状や倦怠感、肌荒れなどの不調が現れることもあるのです。
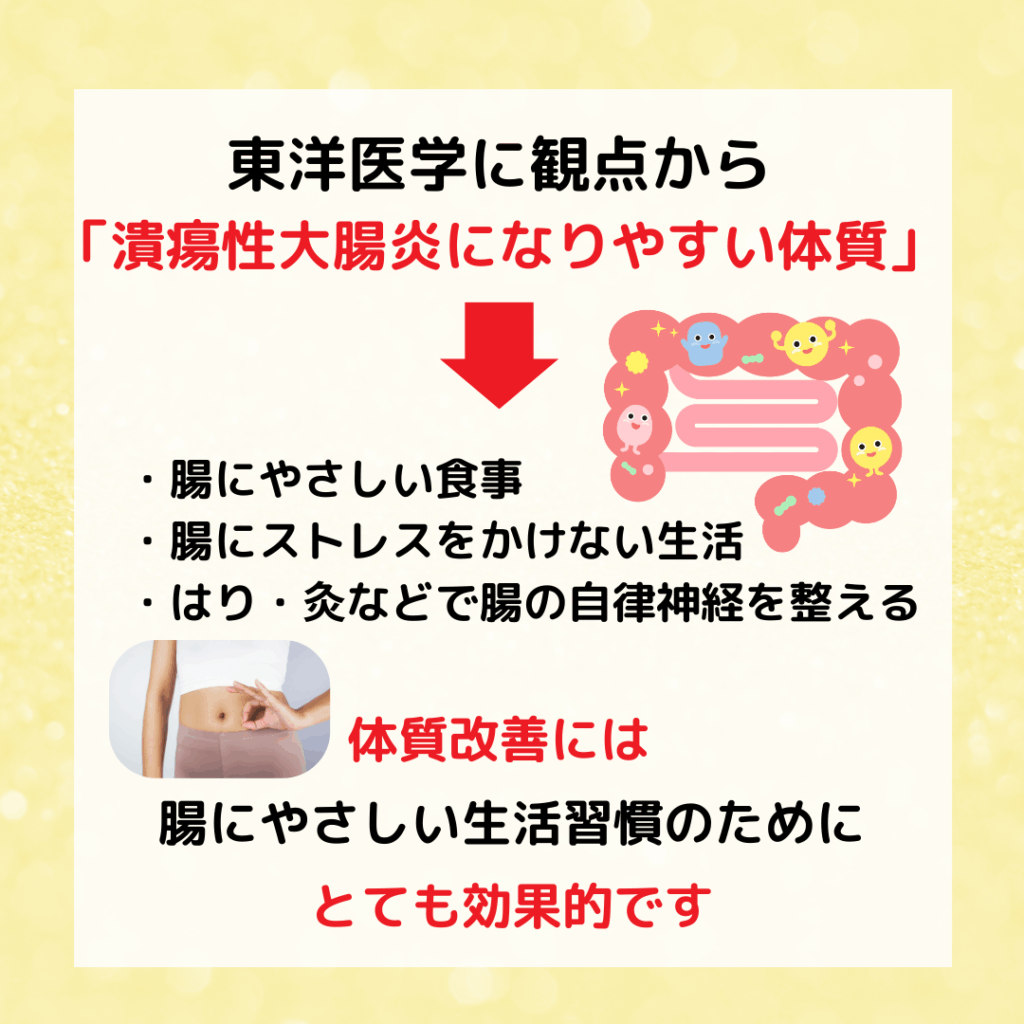

潰瘍性大腸炎を根本から改善していくためには、日々の生活習慣、特に「何を食べ、何を避けるか」が非常に重要になります。白砂糖、小麦粉、乳製品はどれも食生活に深く関わっており、完全に避けるのは難しいでしょう。しかし、腸にとってはこれらが強いストレスとなるのは確実であり、炎症を助長する可能性があります。
また、これらの食品を控えるだけではなく、東洋医学的な視点から「潰瘍性大腸炎になりやすい体質」自体を改善していくことも大切です。
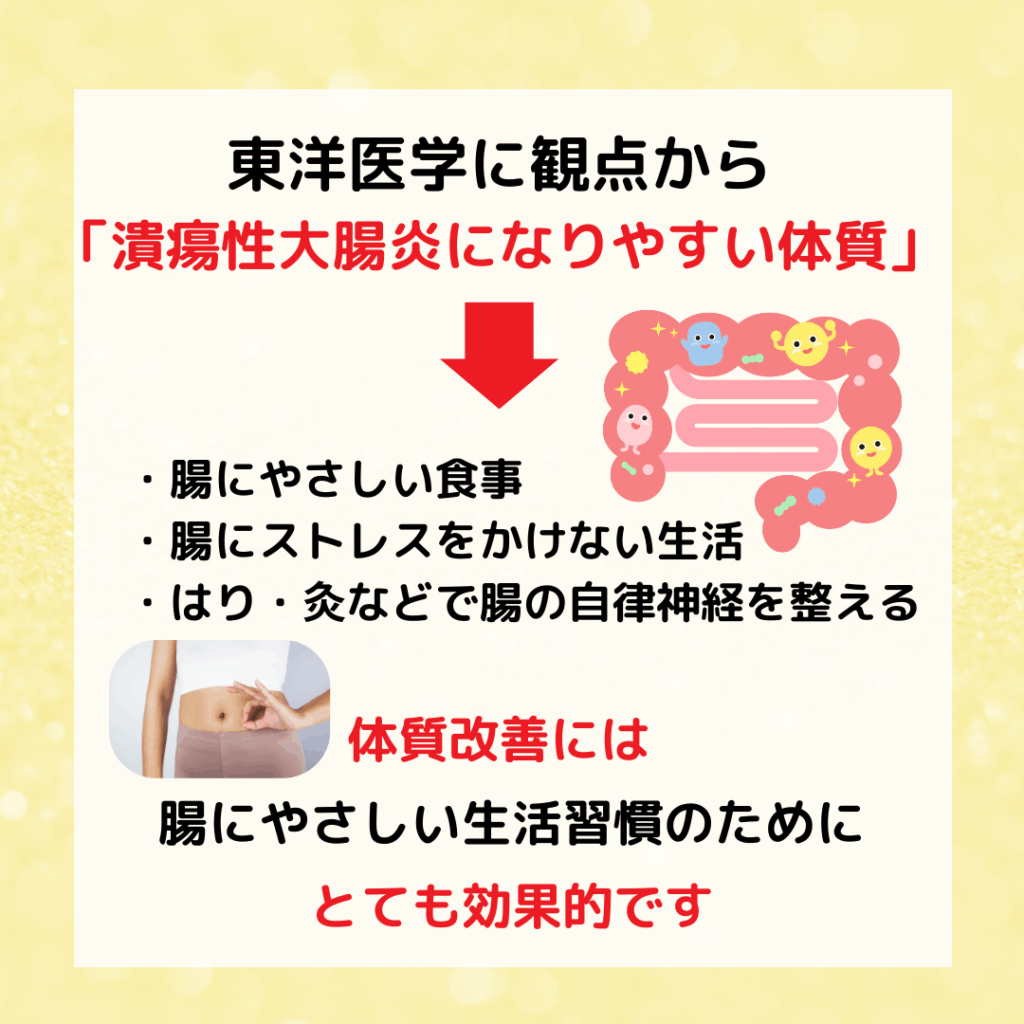
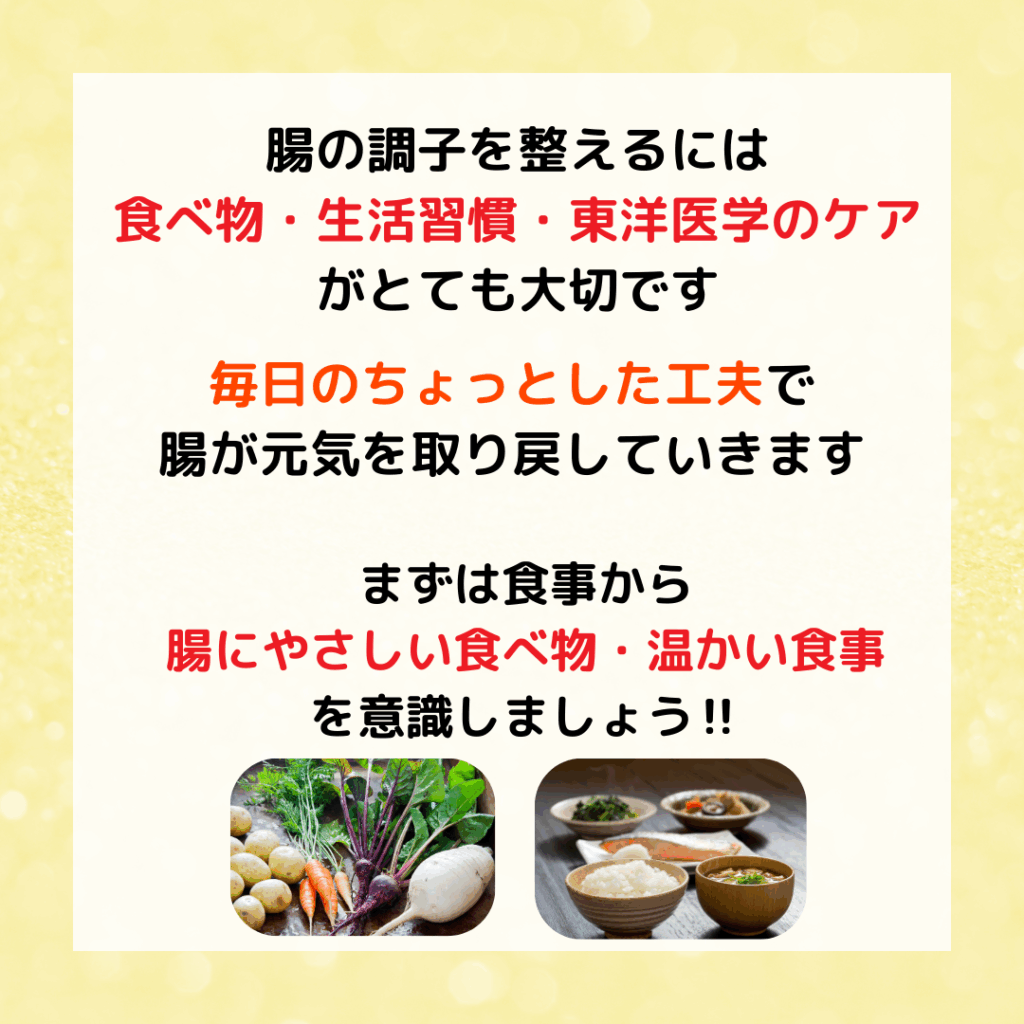
体質改善のためには、
腸にやさしい生活習慣のために
といった取り組みがとても効果的です。
・腸にやさしい食事
・腸にストレスをかけない生活
・はり灸などで腸の自律神経を整える
腸の調子を整えるには、食べ物、生活習慣、そして東洋医学のケアがとても大切です。特別なことをしなくても、毎日のちょっとした工夫で、腸は元気を取り戻していきます。
まずは食事から。腸にやさしい食べ物や温める食事を意識しましょう。


おすすめの食品
・発酵食品(納豆・味噌・塩麹・漬物など)
・食物繊維が豊富な食品(根菜類・わかめ・こんにゃく・雑穀など)
・温かい飲み物(お白湯・ほうじ茶)
逆に、腸の負担になりやすい食品もあります。疲れているときや不調を感じるときは、以下のものが控えるべき食べ物です。
・白砂糖を多い甘いお菓子・ジュース
・冷たい飲み物やアイスクリーム
・スナック菓子・加工食品
・香辛料など刺激の強い食べ物
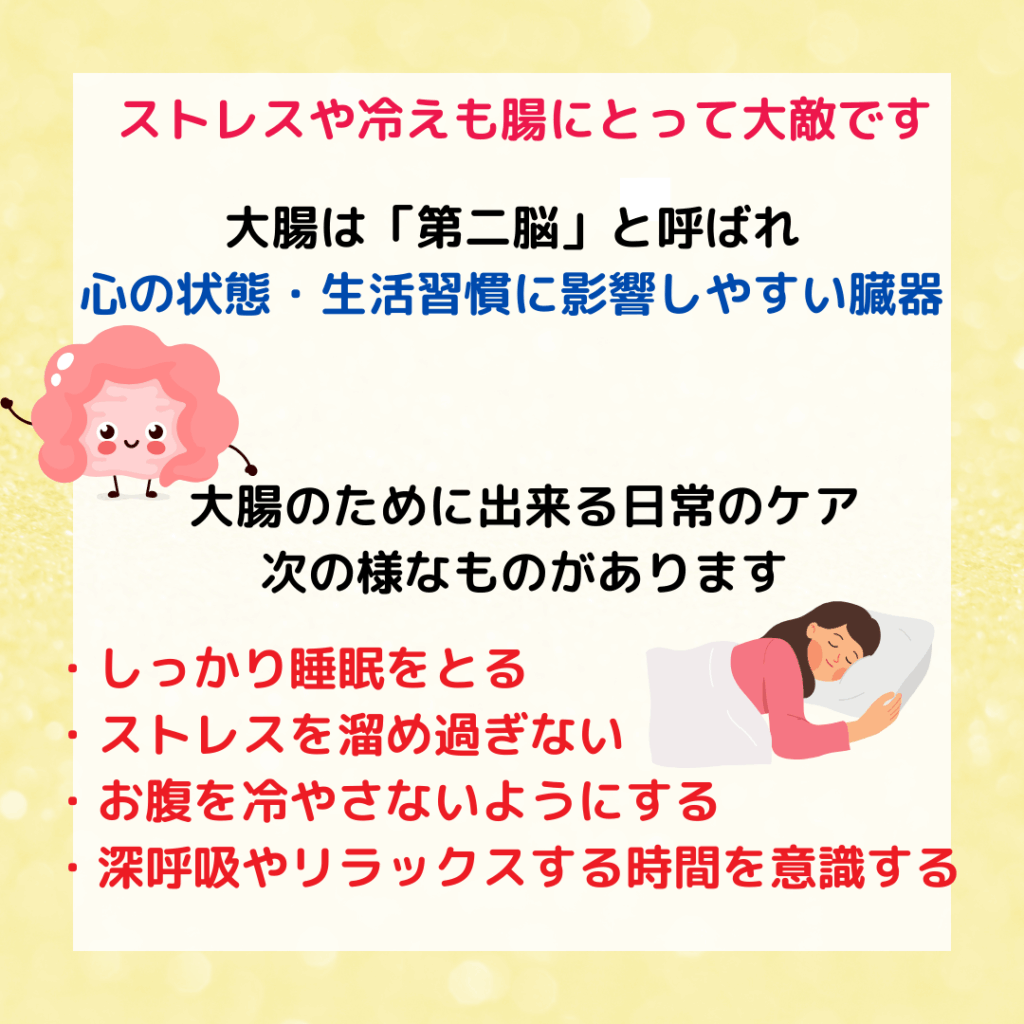
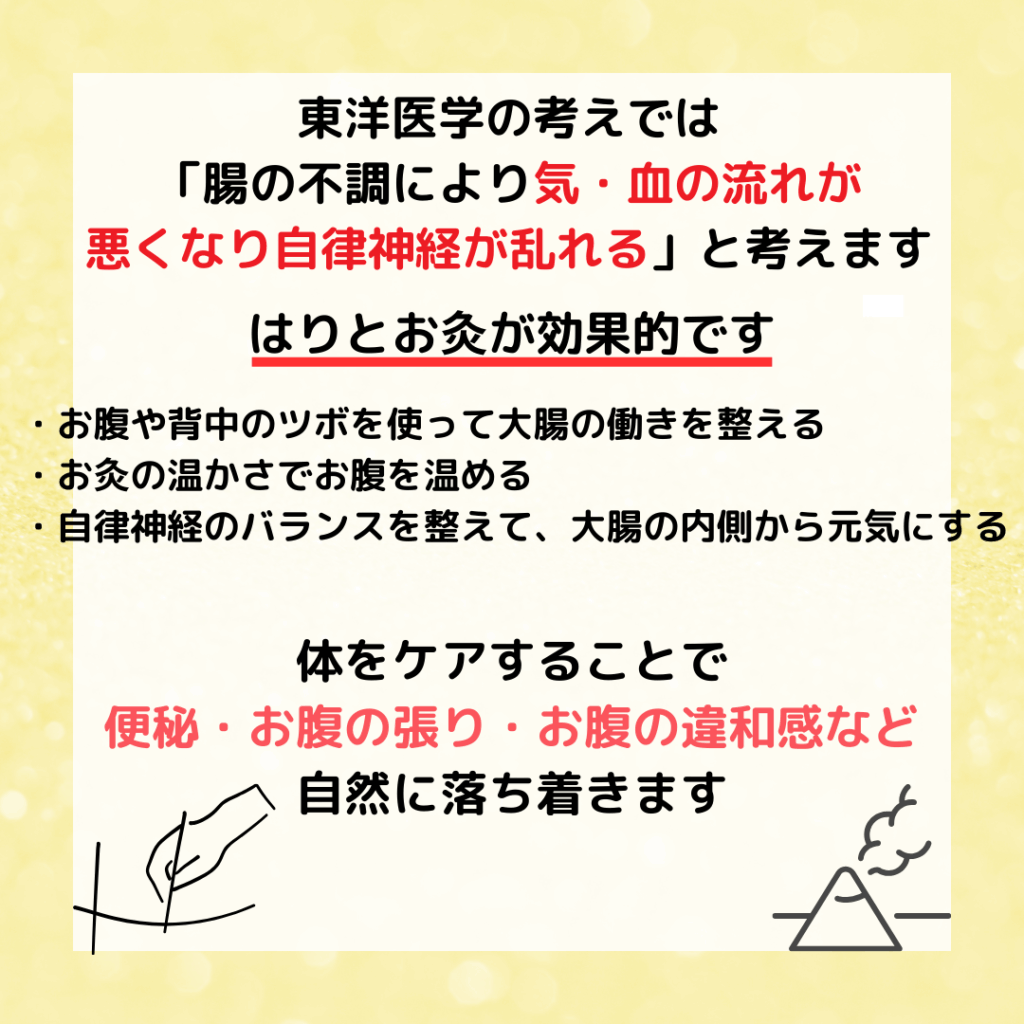
ストレスや冷えも、腸にとっては大敵です。大腸は「第二の脳」とも呼ばれるほど、心の状態や生活習慣の影響を受けやすい臓器です。大腸のためにできる日常のケアは次のようなものがあります。
・しっかり睡眠をとる
・ストレスを溜め過ぎない
・お腹を冷やさないようにする
・深呼吸やリラックスする時間を意識的にとる
そして、東洋医学の考えでは「腸の不調により気・血の流れが悪くなり自律神経が乱れる」と考えられています。そんな時は、はりやお灸がとても効果的です。
・お腹や背中のツボを使って大腸の働きを整える
・お灸の温かさでお腹を暖める
・自律神経のバランスを整えて、大腸の内側から元気にする
こうしたケアを取り入れることで、便秘、ガスの張り、お腹の違和感などが自然と落ち着いてわいくことが多いです。
腸は「第二の脳」とも呼ばれ、腸にはたくさんの神経が集まっていて、自律神経や気分にも影響します。幸せホルモンの多くも腸で作られていて、腸が整うと心も体も元気になります。

潰瘍性大腸炎でお悩みの方は、
「難病だから一生付き合うしかない」と諦めずに、腸にやさしい生活と体質の見直しを始めてみてください。少しずつの変化が、体に大きな改善につながります。
当院では、お一人おひとりの状態に合わせたアドバイスと鍼灸施術を行っています。
お気軽にご相談ください。
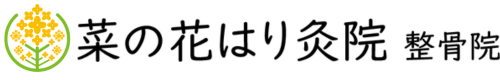

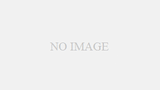

コメント